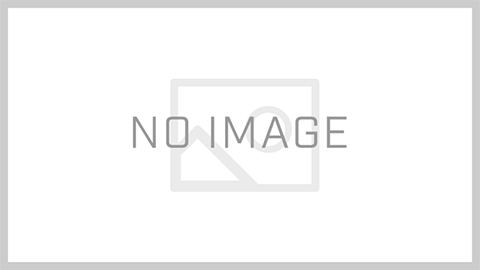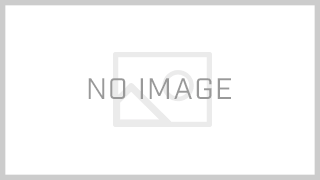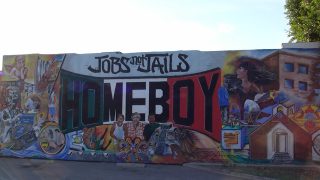世界的に見ても年々とその数が目減りしているレコードショップや
アナログな媒体を扱っている業種。
一部のコアな商品を扱っているマニア向けのショップなら
ファンに支えられながら、ミニマムに経営を続けていっているかもしれませんが
顧客のターゲット層をメインストリームに絞ったようなショップの
経営は日に日に厳しくなって、日本でも年々とその数が減っています。
しかしここへ来て
少しづつではあるが、音楽業界やクリエイティブな職業を生業とする
アーティストの制作物を中心に、アナログ志向になっているように感じます。
ミュージシャンの間ではソフトウェアで音源を用意する人もいるが
未だに、アナログ=ハードシンセにこだわって作っている人もいます。
イラストレータなども、デジタルツールに走ってみたものの
やっぱり、アナログな制作手法に帰ってきたり
しかしこのような、変化はクリエーターとしてみると
それは、単に音質や質感だけの問題ではなく
操作性=直感性なども重視しているように感じます。
例えばミュージシャンの中にも、すべてをソフト(PCの中)で
済ませてしまおうと思っている人と、アナログの機材を必ず通して作品を仕上げたい。
などと、いろいろな嗜好や意見があります。
以前のサイトでも紹介したこのショップOOGA BOOGAの
商品のラインナップをみてみると、非常にアナログ的な商品が多いし
それらを、求めるユーザーも同店のL.Aコミュニティーには存在している。
むしろアナログであるからこそ、それがウリとなっている
特にMP3、MIXCDの全盛の今にMIXTAPEのリリースを促したり
L.Aの人気レーベルStones Throw(ストーンズ・スロー)
なども、積極的にバイナルのリリースを行っています。
同レーベルの代表でもある、Peanut Butter Wolf(ピーナッツバターウルフ)は
LAのバイナル製造会社がなくなるまで、バイナルと作っていきたいと意気込んだメッセージもあったくらいです。
Stones Throw(ストーンズ・スロー)は
元々バイナルカルチャーからスタートしたレーベルという経緯もありますが
やはりここでも、アナログで存在しているというパッケージの重要性が
明確になっている証拠でしょう。
その商品やモノ、サービスによっては
デジタルで存在している必要があるモノと、アナログ=モノとして存在していなければ
魅力的ではないモノ、そのように需要が分かれているようです。
時代によって、淘汰されていくものと
古くても、それが”アジ”となって残されていくモノ
今後も、ますますその傾向が強くなっていくんのではないでしょうか。
現にL.Aのローカルなレコードショップでもスタッフと話した機会に聞いた話だと
MP3よりも、パッケージ化されたCD,DVD,MIX CDの方が売れ行きがよいようで
特に限定化された、CDやDVDは売れる傾向にあるとの事。
また、著者の友人が2年ほど前からアメリカはニュージャージーにて
ビンテージキーボードや、デジタル楽器・ソフトウェアではなく
アナログのハードウェアの専門ショップを営んでいるんですが
修理やメンテナンスを行っているという事もあり
地元アーティストや、遥々アメリカの田舎からビンテージキーボードの修理も
依頼するような、アーティストもいたりと、楽器販売の商売も順調のようです。
彼は、昔マンハッタンで楽器店を営んでいて
当時は、そこそこの商売をしていたようですが
ミュージシャンの使用楽器の環境変化や業界のシステム変更により
一度は、お店をたたみましたが、改めてアナログに帰ることによって
本来のあるべき楽器店として息を吹き返したようです。
以上の、ことを考えると
アナログリバイバルというのも、デジタルが行き過ぎた時に起こる結果なのかもしれません。
デジタルで作られたものは、タイミングやサイズすべてか均一化して
キッチリしています。
クリエイティブな分野では正確過ぎたモノは、ゆとりがなく
一見するとキレイですが、長くは愛され続けるようなモノなのではないかもしれませんね。
DVD L.Aコミュニティー L.Aの人気レーベル MIX CD Peanut Butter Wolf(ピーナッツバターウルフ) Stones Throw(ストーンズ・スロー) アナログ リバイバル アメリカはニュージャージー ハードシンセ ビンテージキーボード マンハッタン レコードショップ ローカルなレコードショップ 楽器
スポンサーリンク